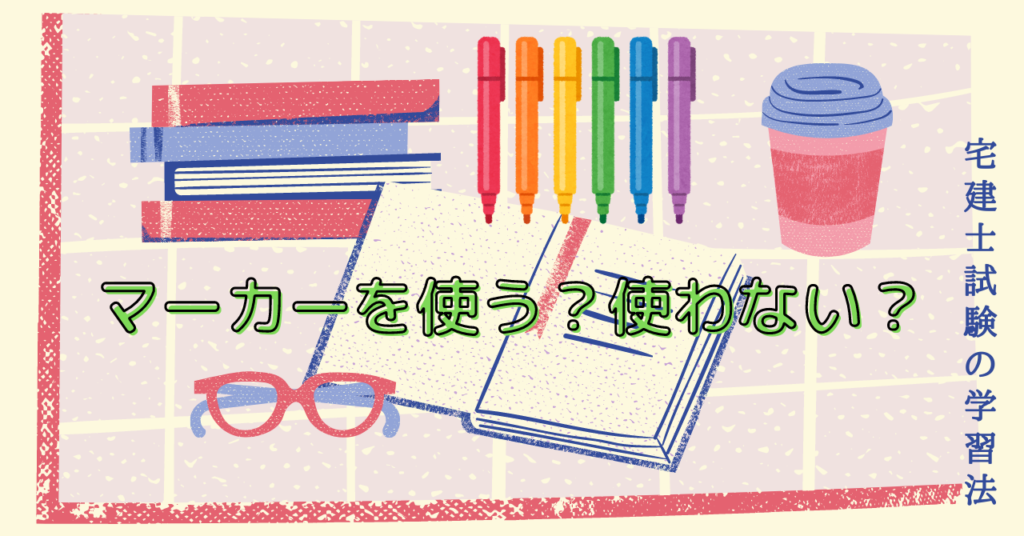書店に行くと、かなりの種類の宅建士関連テキストがあります。
その中でどれを選んで学習するか、それを決めるのはなかなか難しいことかもしれません。
そこで今回は、独学で宅建士試験を受けた私が実際に使用していたテキストを紹介します!
おすすめできるテキストには違いありませんが、レイアウトなど個人差があったりするものですので、最終的には自分にあっていると感じるテキストを選ぶようにしましょう!

どうやってテキストを選ぶか問題
みなさんはテキストを選ぶときに、どのような基準で選びますか?
パッと見の印象、内容の濃さ、評判・・・
宅建士試験のようにテキストの種類が多いと、色々と比べながら決めることになると思います。
この中で気を付けて欲しいのが「評判」です。
アマゾンなどで書かれているレビューには、それぞれのテキストのいい部分やイマイチな部分が書かれています。
しかし、それを鵜呑みにしてしまうのは結構危険だったりします。
レビューには合格者以外のものが結構な割合で混じっていたりします。
合格者以外のレビューって、あまり参考になりませんよね。
逆に、合格者はもうテキストを買う必要がないので、レビューする機会がそもそもなかったりします。
評判だけでテキストを選ぶと結構な確率で失敗しますので、そのあたりは注意するようにしましょう。
実際に使用したテキスト
ちょっと話が脱線してしまいました。
市販テキストを使って独学で合格した私が「実際に使用していたテキスト」を紹介します!
それが『パーフェクト宅建士 基本書』です!
住宅新報出版ということで、宅建といえばここ、みたいな信頼があります。
LECやTACのような総合資格スクールとは違い、不動産関連に特化した出版物が多いです。
「パーフェクト宅建士」には、テキストの他にも問題集や要点マスター(要点整理集)があり、パーフェクト宅建士シリーズで宅建のテキスト類を一通り揃えることができます。
また、2022年度からは「パーフェクト宅建士 一問一答」がポケット版になるということで、気になっているところです。
これまではテキストと同じサイズのA5サイズでした。
パー宅の特徴
パーフェクト宅建士(通称:パー宅)基本書の特徴を簡単に書いていきます。
個人の感想も含みます。
特徴1 圧倒的なボリューム
パー宅は「ガチ」のテキストだったりします。
そのくらいボリュームがあります。
ページ数も多めですが、1ページに書かれている文の量が多いです。
そのため、他のテキストよりも多くの知識をつけることができるテキストとなっています。
最近の難化傾向にある宅建士試験を確実に突破するには、パー宅くらいの知識はつけておいた方がいいのではないか、と感じます。
合格を本気で狙いに行く受験生はパー宅1択かもしれません。
特徴2 理解しやすい工夫がされている
ぎちぎちに文章が書かれているわけではありません。
図表も所々にありますし、法律用語の解説などもあったりするので、実際は学習しやすいテキストとなっています。
一部の意見では堅苦しすぎるという意見もありますが、図表や用語解説をうまく使えば決して難しくないと思います。
むしろ、実際の本試験ではガチガチの言い回しの文章が出てくるわけですので、それに慣れる意味でも、しっかりと用語の確認をしながらテキストを読み進める癖をつけておいた方がいいように思います。
なぜパー宅を選んだのか
パー宅を選んだ理由としては、「ボリューム」の要素が一番大きかったです。
ボリュームの多さは一見デメリットのようにも感じるかもしれません。
でも、実際は逆です。
文章が多いということは、それだけ丁寧に解説してくれていることの裏返しでもあります。
なぜそのような規定になっているのか、のように、結論だけでなく理由が書かれていることで知識の吸収がスムーズになります。
結論だけだと丸暗記になってしまいがちですので、理解するためにも必要な「ボリューム」だったりします。
パー宅をしっかりこなせれば自信もついて試験に臨めるのではないか、と考えたわけです。
その他の理由として挙げるとすれば、2色刷ということです。
最近のテキストはフルカラーのものもあったりしますが、個人的には2色刷の方が見やすかったりします。
まぁ、このあたりは好みの問題ですけどね(笑)
あとがき
パー宅はじっくり学習できるという受験生にはもってこいのテキストだと思います。
逆に、直前期で詰め込むという学習にはあまり向いていません。
それくらい、時間のかかるテキストです。
ツイッター始めました!フォローよろしくお願いします!
Follow @sapphire_takken
ランキング参加中!