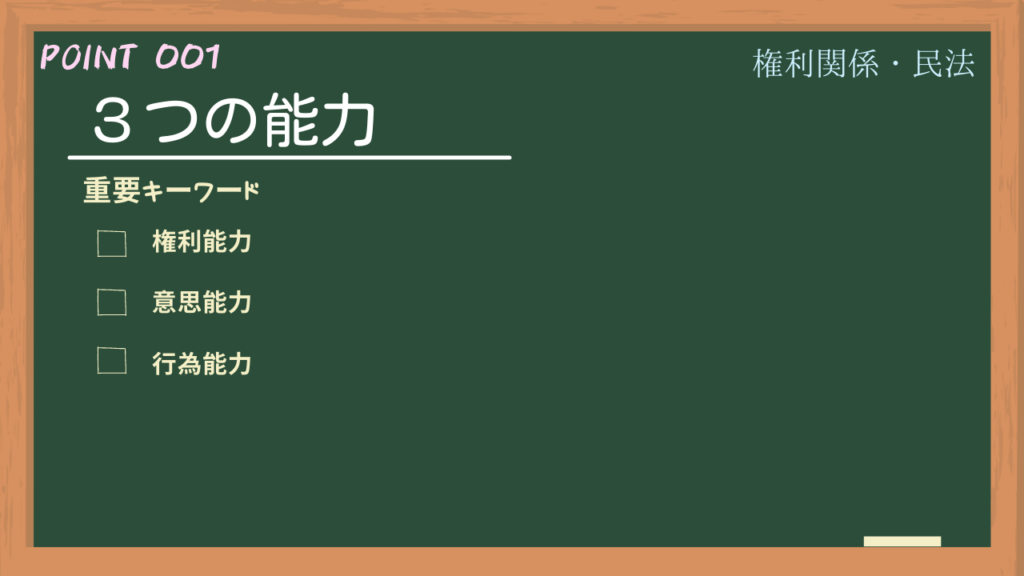テキストを一通り読み終わって、いざ宅建士試験の過去問に挑戦してみると、意外と高得点が取れることがあります。
完成度が高まってくると40点台を連発するようになるかもしれません。
その一方、模擬試験や本試験になると過去問の時のようにうまく点数が取れなくなるものです。
そこで、今回はその理由について解説していきます。
本試験できっちり点数を取りたいという受験生は必見です!

過去問の点数はあてにしない
過去問1年分を通しで解いてみることそれ自体はとても有意義です。
時間配分を知ることができますし、集中力が持つかどうかのチェックもできます。
ただ、そのときに点数を意識しすぎないようにしましょう。
過去問で点数を取ること自体、それほど難しいことではありません。
ある程度学習が進めば、合格点以上の点数を連発するようになってきます。
よほど点数が悪ければ別ですが、35点以上取れるようになったならば点数で一喜一憂するのはやめておきましょう。
過去問で点数がとりやすい理由
ではなぜ、過去問で点数がとりやすいのでしょうか。
答えは割と単純で、テキストが過去問ベースで書かれているからです。
一度出題された問題で重要そうな部分は、次の年度からのテキストに掲載されます。
つまり、今あるテキストには過去問の重要部分が凝縮されているのです。
そのテキストを使用して学習しているわけですので、過去問がある程度解けて当然なのです。
よほどの捨て問は別ですが・・・
模試・本試験は未知の世界
逆に言うと、過去の問題には強いテキストも、未来の問題にはめっぽう弱かったりします。
模試や本試験問題は、テキストを制作している段階では未来の問題ですので、あくまでも「予想」でしかありません。
その予想が当たればその関連の問題が出ますし、外れればテキストにない論点で問題が出たりします。
そうなると、模試や本試験で点数が伸び悩むのは当然のことです。
過去問での点数は、模試・本試験では役に立たない情報なのです。
模試・本試験で点数を伸ばすには
模試・本試験では点数が伸びにくいという話だけでは受験生は満足できないと思いますので、点数を伸ばす方法を簡単に紹介しておきます。
まず、先にも述べたように、過去問の点数は気にしないことです。
過去問でいくら高得点でも、模試や本試験でも高得点が出るとは限りません。
むしろ、変な慢心で点数が伸びないリスクすらあります。
過去問は時間配分や弱点の炙り出しを目的にして、年度の点数は無視してオッケーです。
そして、テキストを信頼してしっかり周回することです。
確かに、テキストが未知の問題に対応できているかどうかは怪しいと感じることもあるでしょう。
ただ、そのテキストをしっかりと理解しておけば確実に合格点を超えるくらいの点数がついてきます。
これは市販テキストどれを選んでも同じことです。
一度決めたテキストを信頼して、最後まで何度も周回させながら理解を深めていくようにしましょう。
コツコツ着実に学習することが大切です。
あとがき
宅建士の試験時間は50問で2時間です。
1問あたりでは2分24秒になります。
この時間が早いと感じるか遅いと感じるか、それを見抜くためにも1年度分を通しで解くことをおすすめします。
個人的には1問あたり2分平均くらいまで解くスピードを上げられればいいのかなと思います。
50問で1時間40分なので、見直しをする時間も確保できますよ。
ツイッター始めました!フォローよろしくお願いします!
Follow @sapphire_takken
ランキング参加中!